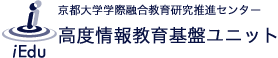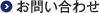ユニット提供科目
- 現在の位置 : ホーム
- ユニット提供科目-科目内容
- 情報基礎[全学向]
情報基礎[全学向]
授業の概要・目的
情報とは何か,情報の処理や計算とはどのようなものかについて,情報の量,情報の表現,情報の伝達,計算の表現,計算の量などの観点から学ぶ.また,現在のコンピュータ,人工知能,情報ネットワーク,様々な情報システムなどがどのような仕組みで動いているのかについても取り上げる.
到達目標
情報とは何か,情報の処理や計算とはどのようなものかについて学ぶことにより,情報という観点からの問題の捉え方を身につけることを目指す.また,現在のコンピュータ,人工知能,情報ネットワーク,様々な情報システムがどのような仕組みで動いているのかについて学ぶことにより,現代情報化社会における知的活動および一般生活において必要となる情報利活用能力の基礎となる知識を身につける.
授業計画と内容
以下のような内容について授業を行う予定である.
[第一部]情報
01 情報とは何か:主観確率,ベイズの定理(田島)
02 情報の量:平均自己情報量,エントロピー(Huang)
03 機械のための情報の表現:アナログとディジタル,誤り訂正符号,データ圧縮,公開鍵暗号(東風上)
04 人間のための情報の表現(1):情報の変換,統計データの表現,人間の認知特性,文化依存性(田島)
05 人間のための情報の表現(2):ヒューマンインタフェース(東風上)
06 人間と機械をつなぐ情報:ロボティクス,ヒューマンロボットインタラクション(東風上)
[第二部]知能
07 人工知能とは何か(1):人工知能の歴史,機械学習,深層学習,生成系AI,説明可能AI(Huang)
08 人工知能とは何か(2):自然言語処理,大規模言語モデル(ChatGPT等)(Huang)
09 人工知能と社会:人工知能と倫理,ロボットと倫理,生成系AIと著作権(東風上)
[第三部]計算
10 計算とは何か:論理回路,有限状態機械,チューリングマシン,ラムダ計算,コンピュータ,計算不可能な問題(田島)
11 計算の表現と量:アルゴリズム,漸近的計算量(Huang)
12 計算のための情報の表現:データ構造,関係,グラフ,一意性,冗長性(田島)
13 複数処理の実行・複数主体による処理:スケジューリング,並列処理,分散処理,OSの役割,インターネットの仕組(田島)
14 情報に基づく意思決定:ゲーム理論(田島)
15 フィードバック(田島・東風上・Huang)
履修要件
特になし
成績評価の方法・基準
授業期間中にほぼ毎週課す課題に対する提出内容により評価を行う.評価の際には,本講義で学ぶ「情報とその表現や処理とはどのようなものか」「コンピュータや情報システムはどのような原理で動いているか」などの知識について,その技術的な詳細を正確に覚えているかどうかよりも,各所各所の要点,および,それらの間の関係の全体像を,自分の言葉で説明でき,かつ,他の分野に応用できる程度に体得できているかを評価する.
教科書
使用しない
参考書等
授業中に紹介する
その他(授業外学習の指示・オフィスアワー等)
授業資料や演習問題の解説資料などを用いて毎授業ごとに復習を行うこと.また,事前に授業資料が配布されるなどにより授業内容が事前にわかっている回については,取り上げられる概念などについて各自で調べて予習を行うこと.